- コンサルって中身がないって言われているけど、本当?その理由は?
- どうしたら中身がないコンサルタントと言われずに済む?
コンサルについて調べていると、「コンサルは中身がない」という意見も耳にしますよね。
コンサル転職を考えている方にとって、「中身がない」と言われてしまうと、自身のキャリアでコンサルを選ぶことを悩む方もいらっしゃるかもしれません。

私自身、外資の戦略コンサルに新卒で入る際、「本当に良いのだろうか?」と気がかりでした。
この記事のポイント
- 「中身がない」とは、内容の問題だけでなく、外見と内容が釣り合っていない状態
- コンサルの外見は簡単に「それっぽく」なる一方、良い内容を作れるようになるには時間がかかる
- 「中身がないコンサル」と言われるのは、外見と内容の成熟期間のギャップが要因
- コンサルキャリアでギャップを減らすには個人の努力に加えてファーム選びが非常に重要
この記事では、新卒で外資系戦略コンサルに入社して、現在は日系大手メーカーで働く筆者が、コンサル・クライアント双方の立場での経験を元に「コンサルって中身がない」の実態を解説します。
ぜひ最後までお読み下さい。
コンサルの中身がないと言われる要因
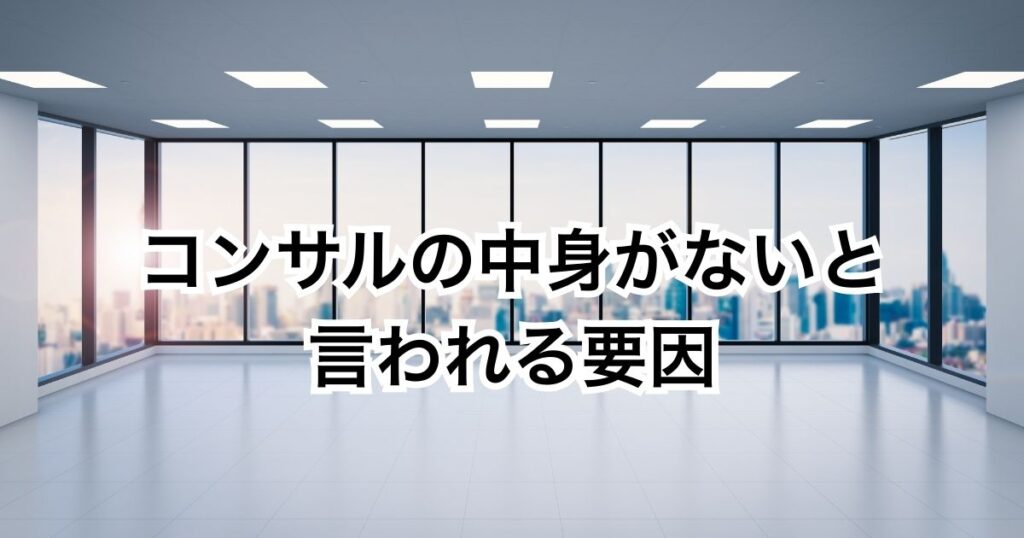
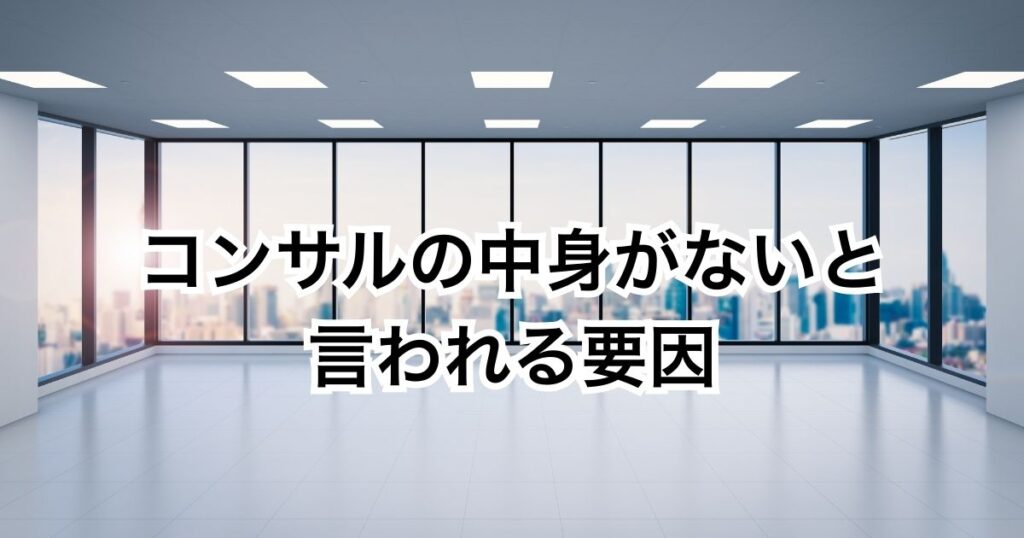
中身がない=外見に対して内容が伴っていない
人が「中身がない」と言うのは、単に内容が浅いだけでなく、外見との不釣り合いさが感じられる時です。
外見について明言していなくても、人は外見とのギャップを見ています。ギャップが大きければ大きいほど「中身がない」と評されてしまいます。
コンサルの中身がないと言われているのは、どこかコンサルの外見から感じられる期待値と、コンサルの考える内容のギャップが要因です。
ではコンサルの外見と内容のギャップはどこから生まれるのでしょうか?
コンサルの外見と内容は成熟期間のギャップが大きい
コンサルの外見と内容にギャップが生まれるのは、それぞれが一定水準に成長するまでの成熟期間の差が要因です。
コンサルの外見は、成果物の見た目だけでなく、コンサルタント本人の服装や持ち物、コンサルファームの醸し出すブランディングがあります。
コンサルの成果物の見た目やコンサルタント本人の身なりは簡単にそれっぽくなります。
コンサルファームのブランディングは、コンサルファームに入社した時点でそのブランディングの恩恵を受けます。
一方、コンサルの考える内容を磨き上げるにはそれ相応の時間がかかります。



パートナーになってようやくコンサルティングがわかるという意見もあるほどです。
直ぐに「それっぽくなる」外見と、時間のかかるコンサルティングの内容。このギャップが「中身がない」に繋がります。
外見と内容について、次章で詳しく解説していきます。
中身がないコンサル詳説:キレイな外見
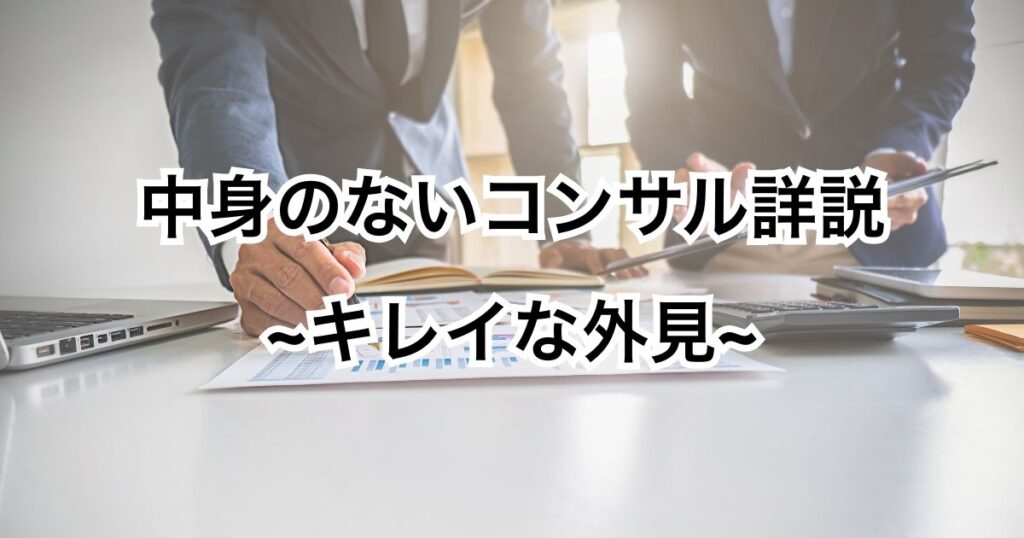
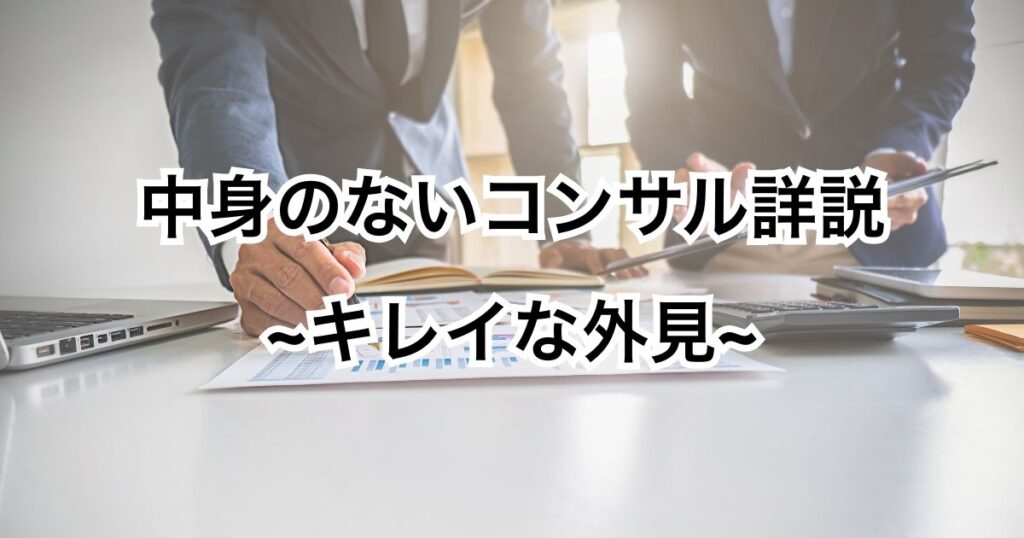
まず初めにコンサルの外見について、次の3つの角度から解説します。
- コンサルのパワポの見栄え
- コンサルタントの身なり
- コンサルファームのブランディング
外見が良いことそれ自体は問題はありません。コンサルティングをする上で見た目は非常に重要です。
しかし、外見だけに頼ってしまうと、コンサルティングの内容次第で「中身がない」となってしまうので注意が必要です。
コンサルのキレイなパワポ
コンサルはパワポは、とにかく細かいところまでキレイに作り込まれています。
見た目を作り込むことは、忙しい顧客がパッと理解するというメリットがありますし、数千万円や億円を超える金額の成果物に相応しい見た目にも繋がるからです。
例えば、コンサルではthink-cellというパワポの図表をキレイに書くための専用プラグインを入れています。
ファームによってはプラグイン自体を自社で開発していることもあります。
パワポで使う色やフォント、余白などもルールが厳密に定められていることも多いです。
外部のレポートでのグラフも、自分たちでわざわざ書き写して、グラフ色やサイズ、データラベル等を調整します。
成果物の見た目は明確にルール化されているので、入社後すぐ身につけることが可能です。
コンサルタント1年目の仕事の1つが「上司の手書きスライドの清書」だったりもすることから、難易度が高くない作業であることがわかります。
「キレイなスライドは書けるが、内容が全然伴っていない」だと中身がないコンサルになります。
コンサルとパワポの関係について、別記事で詳細を解説しています。ぜひあわせてお読みください。


コンサルタント本人の身なり
コンサルタントは自身の身なりに対しても強いこだわりを持ちます。
元々は経営層相手に仕事をするので、失礼がないように、という観点で始まった文化です。
年収も高いため、高級スーツや革靴、腕時計などの身なりにもお金を注ぎ込めるのも要因でしょう。
確かに同じことを言われるとしても、ボロボロの靴やヨレヨレのシャツの人に言われるよりも、ピカピカの靴やパリッとしたシャツの人に言われる方が、説得力があるのもわかります。



某ニュース番組に経歴詐称の経営コンサルタントがいましたが、パリッとした身なりが、彼の信頼に大きく貢献していたはずです。
しかし、これらはあくまで内容が伴っている場合です。
内容が全然伴っていないにも関わらず、身なりだけプロっぽい演出をしても「中身がない」と評されてしまいます。
コンサルファームのブランディング
コンサルティングファームは、自身のコンサルブランドへ明確に投資しています。
都心の一等地にピカピカのオフィスを構えるだけでなく、自分たち発でメディア露出する時も非常にスマートに見えるような演出がなされています。
当然、支援実績も「これでもか」というほどアピールしています。



提案書本編が20ページに対して、Appendixが100ページを超えることは珍しくありません。Appendixには豊富な知見や実績を多数詰め込んでいます。
コンサルティングは提案時点では「考えた仮説」しかありません。
クライアントに対して信頼されなければコンサルティングができないので、ブランドに投資するのは正しい戦略でしょう。
ここで注意すべきは、コンサルタント個人が勘違いしないことです。
有名コンサルファームに入社したその日から、外から見ればピカピカのコンサルタントになります。
しかし、ピカピカなのはコンサルファームです。自身のコンサル力が伴っていないと、「中身がない」となってしまいます。
中身がないコンサル詳説:低品質のアウトプット
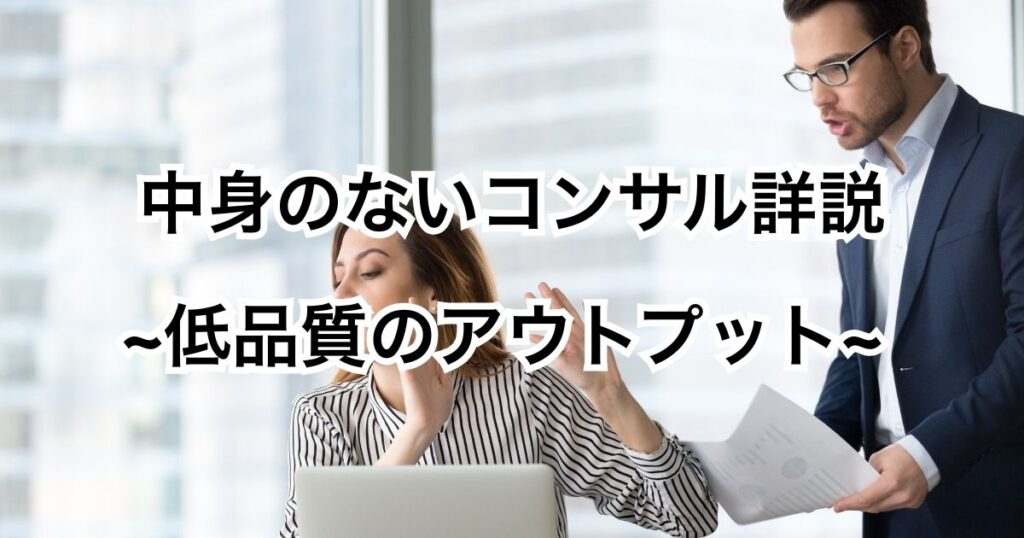
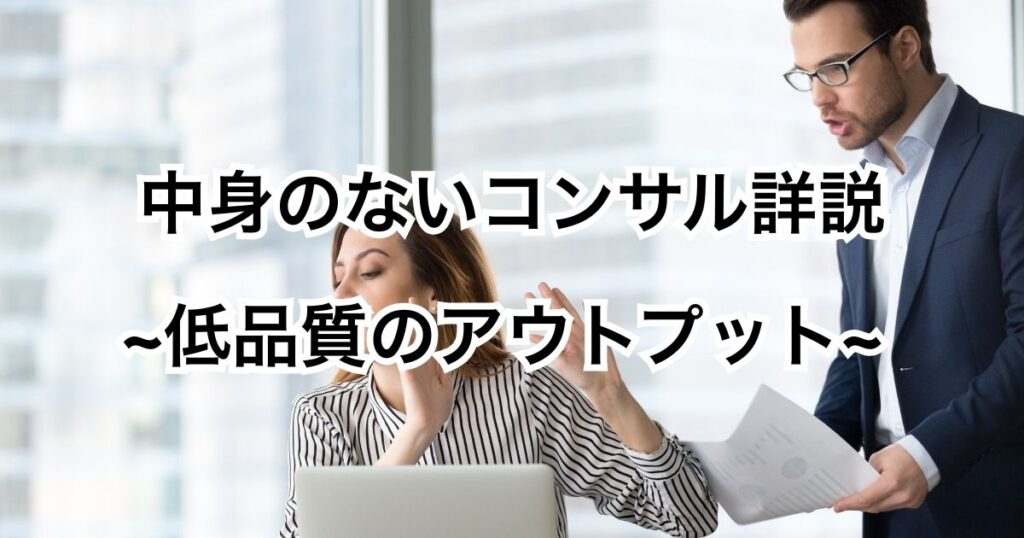
次に、中身がないと言われてしまうコンサルにありがちな、低品質なアウトプットの特徴を解説します。
低品質のアウトプットは、前章の外見の良さと相まって「コンサルは中身がない」と言われてしまうことに繋がります。
解くべき問いに答えてない
1つ目の特徴は「解くべき問いに答えてない」です。
顧客の依頼はふわっとしていることが多いですが、そこから解くべき問題設定を丁寧に行わないと低品質なアウトプットとなってしまいます。
例えば、「利益を増やしたい」という顧客がいたとします。
利益を増やすためには、コストカットと売上増の両方のアプローチがありますが、「どちらに取り組むべきか?」という問いを設定せず、いきなり「コストカットするには?」という問いから始めてしまうようなケースです。
シンプルな問いであれば、適切に問題設定できるかもしれないですが、実際のコンサル案件では状況が複雑あり、問題設定が難しくなります。
顧客が「知りたい」と言ってきた問いに単純に答えれば良いわけではない点も、問題設定の難しさを助長します。
顧客が「知りたい問い」が、必ずしも「解く価値があって、解ける問い」でないからです。
解くべき問いを見誤ると、それ以降どれだけ正しく進めても内容が伴わない結果になってしまいます。
一般的な答えしか言わない
2つ目の特徴は「一般的な答えしか言わない」です。
解くべき問いを正しく設定していたとしても、それに対する答えが誰にでも当てはまるような一般論だと顧客は「中身がないな」と感じます。
もちろん、一般的な方法が当てはまる場合もありますが、コンサルファームに依頼するような案件は、基本的には個社事情を勘案しないと解決できないような案件がほとんどです。



そもそも一般論であれば書籍やWeb上に膨大な情報がありますし、昨今であれば生成AIに聞けば教えてくれることも多いですよね。
一般論を個社に当てはめるにはどうしてもカスタマイズする部分があります。一般論のカスタマイズが難しいから、これまで解決できてこなかった、ということもあるでしょう。
いかに顧客に合わせた内容を言えるか?が、「中身がない」と言われてしまうか否かの分岐点です。
ロジック・ファクトの詰めが甘い
3つ目の特徴は「ロジックや裏付けとなるファクトの詰めが甘い」です。
特に顧客から「このファクトからはそれが言えないのでは?」や「論理的に破綻していないか?」との指摘を受けてしまった日には、中身がないと評されてしまっても仕方がありません。
コンサルの基本的なプロセスは、「問いの設定→仮説の構築→検証」の繰り返しです。
仮説検証の時に必要なのが、ロジックやそれを裏付けるファクトの積み重ねです。
このロジックやファクトの詰めが甘く、仮説を検証できていなければNGとなります。
ロジックやファクトを積み上げることよりも、その矛盾点や違和感を指摘する方がはるかに簡単なので、要注意です。



コンサルにとって不利な戦いですが、プロとして仕事をするには必要なことです。
言葉の解像度が荒い
4つ目の特徴は「言葉ひとつ一つのの解像度が荒い」です。
安易にビジネス用語や何を指しているか曖昧な表現を使っている場合、内容が伴っていないことが多いです。
例えば「シナジー」や「戦略的」、「競争優位」など、コンサル界隈でよく使われる言葉や、「検討する」や「確認する」など、具体的に何をするのか明確にならない表現など。
挙げればキリがありませんが、意味を適切に理解して使用していないと「これってどういう意味?」と聞かれた時に答えに窮してしまいます。
もちろん人によって言葉の意味を取り違えていたり、そもそも定義が1つに定まっていない言葉がビジネスにおいては多いです。
学術論文ではないので、厳密な定義は難しいですが、少なくとも自分が発する言葉はどういう意味で使っているのか、明確に説明できることが必要です。
曖昧な表現ばかりだと、「中身がないな」と顧客に思われてしまうでしょう。
コンサル内で連携できていない
5つ目の特徴は「コンサル内で連携できていない」です。
特にプロジェクトマネジャーとスタッフの間での連携ができてないと、途端に中身がないように顧客からは見えます。
例えば、マネジャーとスタッフと分担して作って内容がスムーズにつながっていないようなケース。
使っている表現が揺らいでいたり、そもそも必要のない資料だったり、と様々な連携不足があります。
ひどいケースだと、マネジャーがスタッフが書いた内容を読んでいないかのような時も。
細かく指摘してくれる顧客もいますが、多くの顧客は細かいところまでは指摘してくれず、なんとなく腑に落ちない顔をしたり、全体に対してのフィードバックをしたりするに留まります。



当たり前ですが、顧客がコンサル側を育てるためのフィードバックをする理由はどこにもないですよね。
個別のスライド自体は不自然でなくても、全体でおかしなことになっていれば、「中身がない」となってしまいます。
コンサルって中身がない?よくある質問
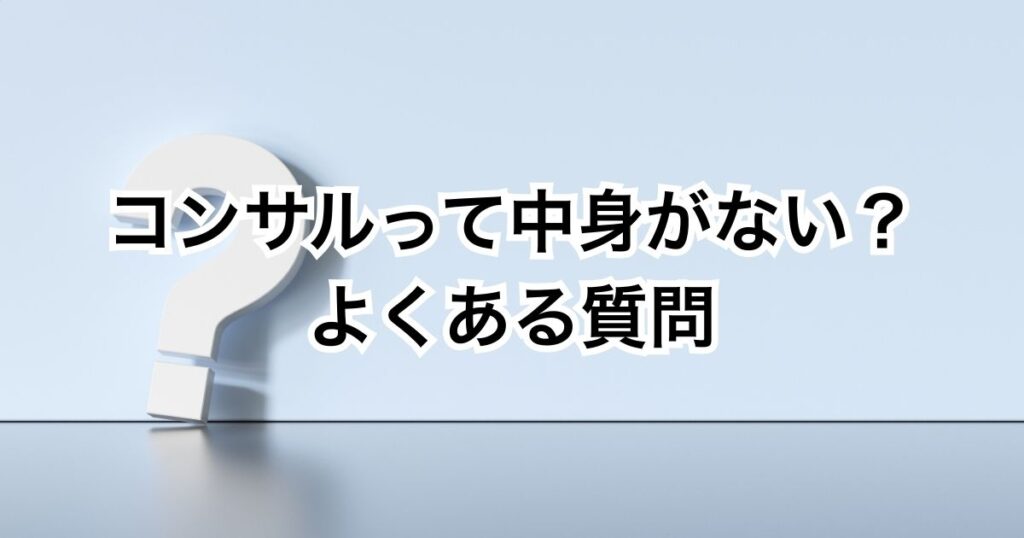
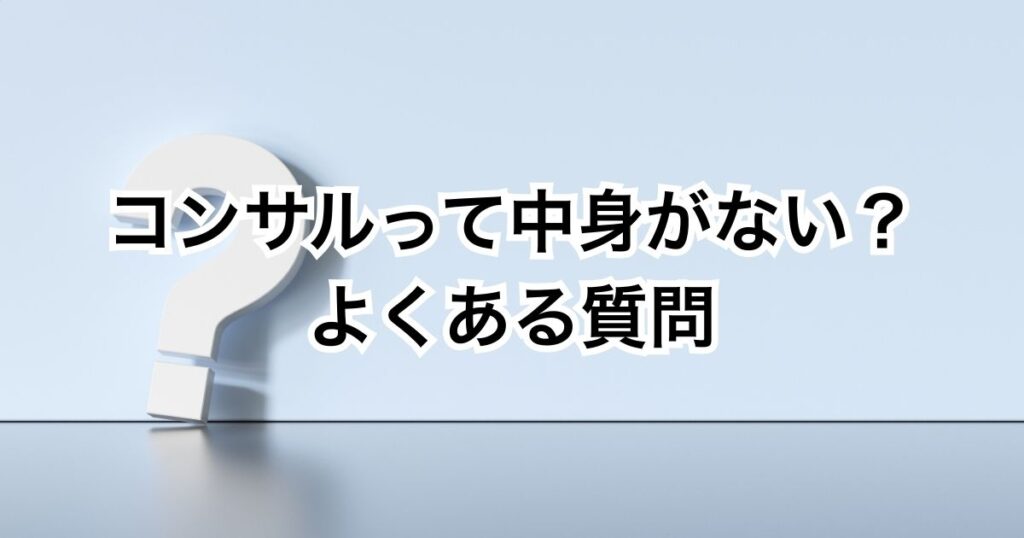
新卒でコンサルにいくと中身がない?
- 新卒でコンサルになると、中身がないコンサルタントになるのか?
-
いいえ。中身がある・ないと、新卒かどうかは関係ありません。
もし仮に新卒コンサルが中身がないのであれば、そもそもコンサルファームは新卒採用をしていないでしょう。
最初から中途採用のみにすれば良いはずです。世の中には、中途しか取らない会社がたくさんあります。
もちろん入社したての新卒ホヤホヤは社会人経験もないため、価値を発揮できる領域は非常に限定的です。
しかし、中途入社であっても、コンサル未経験であれば大して変わりません。どんぐりの背比べです。
詳しくは別記事にて解説しているので、合わせてお読みください。
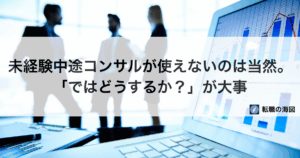
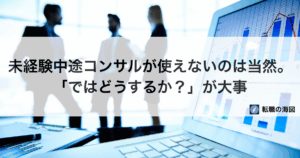
自分でやらないコンサルは中身がない?
- 経営したことがないのに経営コンサルタントをする等、自分でやっていないコンサルは中身がない?
-
いいえ。中身がある・ないと、自分でやっているか否かは関係ありません。
「経営したことないのに、経営コンサルなんてできるわけない」という言質を時々聞きますが、自分でやったことがないから指南できない、ひいては中身がないというのは論理が飛躍し過ぎています。
逆に経営者であっても経営コンサルができるとは限りません。両社は全くの別職種なのです。
コンサルタントとして価値を発揮さえしていれば、自身で経営をしたことがなくても問題ありません。
詳しくは別記事で解説しているので、合わせてお読みください。
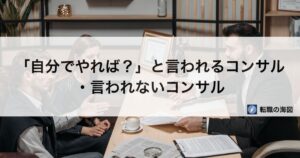
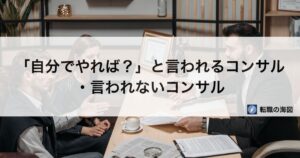
現場を知らないコンサルは中身がない?
- 現場を知らないコンサルは中身がない?
-
はい、現場を知らないコンサルは良い提案をできず、「中身がない」と評される可能性があります。
コンサルの提案には、上述の通り、顧客ならではのカスタマイズが不可欠です。
カスタマイズをする上で、顧客の現場を知っていることは必要不可欠になります。
詳しくは別記事で解説しているので、ぜひお読みください。
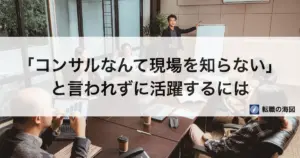
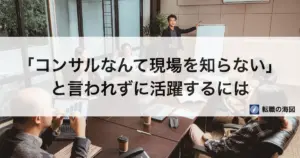
「コンサルって中身がないよね」と言われないために
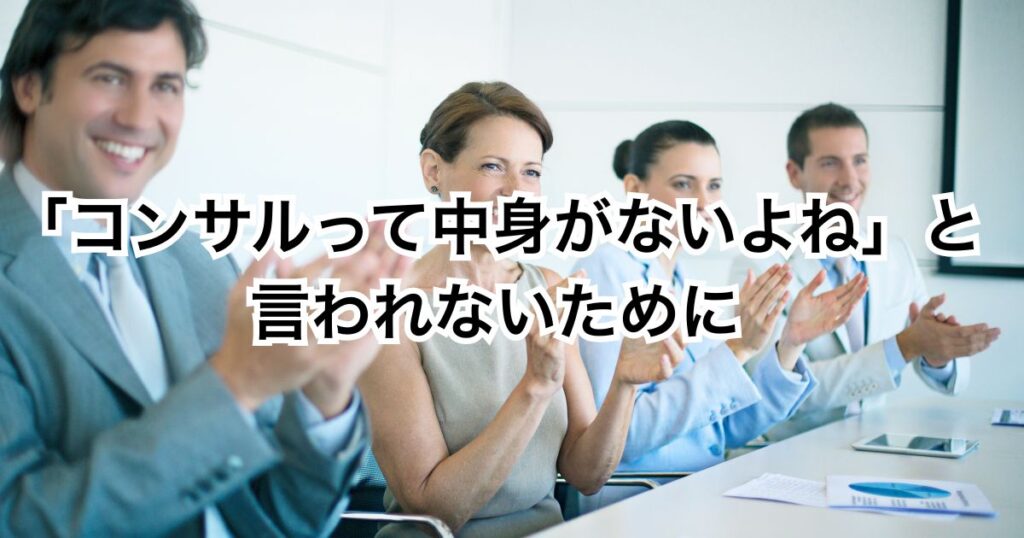
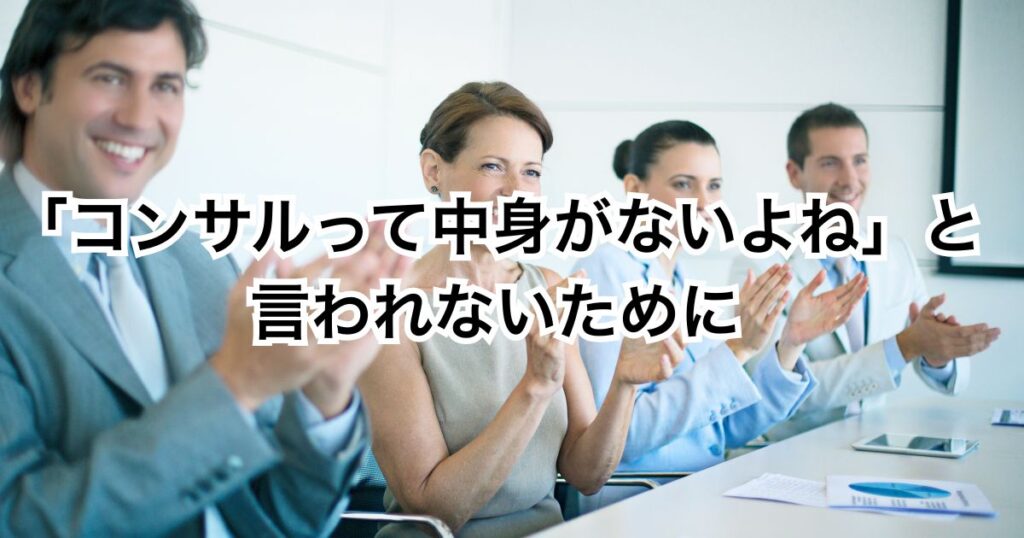
せっかくコンサルになろうと思うのであれば、誰であっても「中身がない」とは言われたくないですよね。
ここでは「中身がない」と言われないためにできるポイントを2つご紹介します。
外見よりも内容を磨く
中身がないコンサルと言われないためにできることの1つは「外見よりも内容を磨く」です。
特に最初の頃はスライドの書き方やエクセルの作り方など、わかりやすいスキルを磨くことに力を注ぎがちです。
もちろんスライドの書き方などのスキルはできて当たり前なので、磨く必要があるのですが、それに逃げてしまってはいけません。



最低限の品質をさっさとクリアできるようになり、1日でも早く本質的な内容を磨くことに注力しましょう。
作業ひとつとっても深く考え、自分が価値を出すことを意識してみてください。
特に入社したての頃はできなくてもある程度は許される環境です。その間に失敗できることは失敗しておきましょう。
自分に合うコンサルファームを選ぶ
中身がないコンサルと言われないためにできることの2つ目は、「自身にあった環境に身を置くこと」です。
中身がある内容になるかどうかは、上司であるマネジャーやパートナーが適切にプロジェクトをマネジメントできるかにかかっています。
良い上司がいる環境に身を置いて、どれだけ学べるか?が重要です。
この時コンサルの”色”も重要です。同じ外資戦略ファームであっても、マッキンゼーとボスコンとベインでは、社員のキャラクターや雰囲気は異なります。外見の雰囲気も違ってくるのです。
自分に合ったコンサルを見つけるには、コンサルに特化している転職エージェントの活用が最も有効です。
彼らは数多くのコンサルファームとの付き合いがあるため、それぞれの特徴を横並びで比較できます。
多くの候補者を見てきた経験から、コンサルを受ける前にどこが良さそうかの当たりをつけることもできます。
今すぐに転職する意向がなくても、コンサル転職に関心があれば、エージェントはサポートしてくれます。ぜひ無料登録をしてみてください。
具体的なエージェントの選び方は別記事で詳しく解説していますので、ぜひお読みください。


クライアント向け:中身がないコンサルに当たった時の対処法
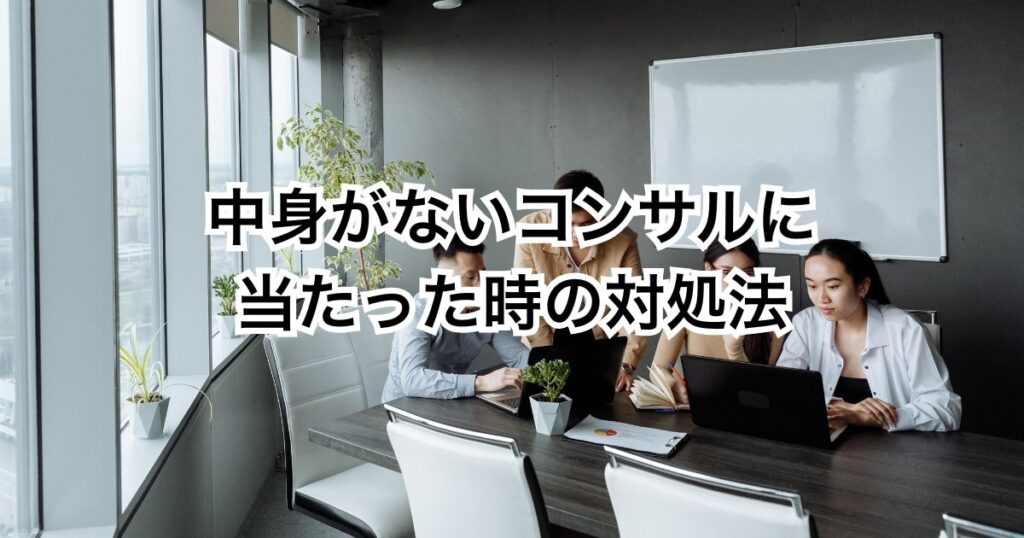
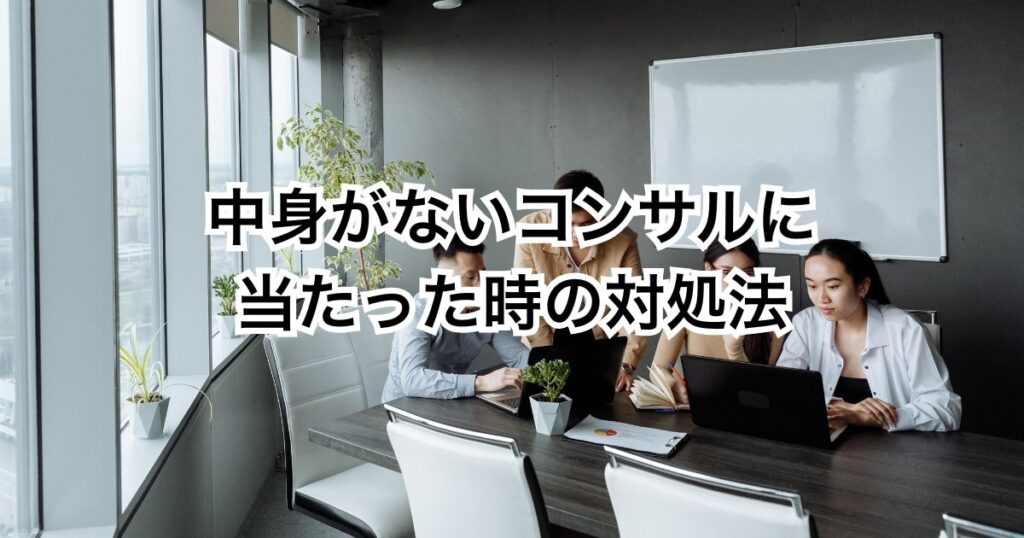
自身の依頼の仕方を振り返る
「中身がないコンサルだな」と感じたら、まずは自身の依頼が適切かを振り返ると良いです。
コンサル側に問題があるだけでなく、クライアント側の依頼が不十分であるケースも少なくないからです。
例えば、「とりあえずなんか気になるから教えて」というふわっとした依頼をしていないでしょうか?
他にも、年度末の予算消化のために、なんとなくの調査を依頼していないでしょうか?
本来5,000万円かかるような内容を、決裁規定や予算に合うように無理な依頼をしていないでしょうか?
本当に優秀なコンサルタントであれば、顧客側の不慣れな部分までカバーしてくれますが、そこまで対応できないケースもあります。
特に金額が小さければ、コンサル側から見ても優先度を上げづらい顧客かもしれません。
コンサルへの適切な依頼の仕方について、別記事にて解説しているので、合わせてお読みください。
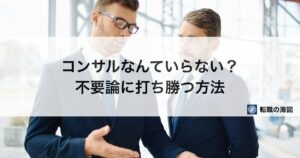
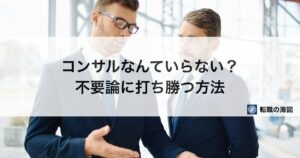
品質責任者にフィードバックする
コンサルに対して適切な依頼をしているにも関わらず、中身がないというケースも当然あります。
この場合は、コンサル側の品質責任者に相談しましょう。
品質責任者は提案書に書いてあることがほとんどです。大抵はコンサルのパートナーや営業担当ディレクターなどが該当します。
「どうも品質がよくない。なんとかならないか?」と率直に伝えてください。
担当者の変更やメンバーの追加アサイン、それでも足りなければパートナー自身が手を動かしたりと、成果が出るように動いてくれるはずです。
コンサルファームを変える
コンサルに対して適切な依頼をしている上に、品質責任者に対してフィードバックをしているのになかなかクオリティが上がらない場合も0ではありません。
このケースでは、コンサルファームを変えることも1つの有効な手立てです。
ずるずると進めているよりも、スパッと別のコンサルに依頼した方が早く解決することも往々としてあります。
この時、同じファーム内で別のコンサルタントに依頼したらいいのでは?と思う方いらっしゃると思います。
しかし、現実的にはファームを変えた方がトータルでプラスになることが多いです。
コンサルファームのパートナーは、同じ領域に何人もいません。例えば、飲料業界に強いパートナーはその人だけだったりします。
また売上責任を負っているので、自分のプロジェクトを他のパートナーに譲ることは基本的に避けたがります。
もう一度コンサルを探して依頼することは骨が折れる部分もありますが、完全な0スタートにはならないはずですので、変えることを厭わない方が良いでしょう。
【総括】中身がないコンサルの実態を総まとめ
最後に、この記事のまとめです。
この記事のまとめ
- 「中身がない」とは、内容の問題だけでなく、外見と内容が釣り合っていない状態。
- 「中身がないコンサル」と言われるのは、外見と内容の成熟期間のギャップが要因。
- コンサルの”外見”は簡単に「それっぽく」なる
- パワポはルールが明確になっており、覚えて早く書けるようにするだけ
- コンサルタントの身なりは、年収が一定あるので良い品で揃えられる
- コンサルファームのブランド力は入社した時点ですぐ手に入る
- コンサルタントとして次の5つをクリアできるようにならないと、良い内容を提言できない。
- 解くべき問いに答えてない
- 一般的な答えしか言わない
- ロジック・ファクトの詰めが甘い
- 言葉の解像度が荒い
- コンサル内で連携できていない
- コンサルキャリアでギャップを減らすには個人の努力に加えてファーム選びが非常に重要。
- 個人の努力は、外見よりも内容を磨くことに注力する
- 自分に合った良いファームを見つけられることも重要
- クライアント向け:中身がないコンサルに当たった時の対処法は次の3ステップ。
- まずは自分たちの依頼が適切か確認
- 適切な依頼をしている上で、コンサルのパートナーにフィードバックする
- それでもダメなら、ファームごと変える



最後までお読みいただきありがとうございました。
ぜひ「転職の海図」をブックマークしていただければ嬉しいです。
